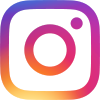EVENT参加受付中のイベント
JSAFはこれから留学を目指す皆さん、またJSAF派遣生を対象にガイダンス、IELTSセミナー、大学情報セッションを随時開催しています。
- 大学別JSAF留学・学内説明会情報
-
各大学ごとの留学プログラムの紹介や学内での説明会/個別相談会情報です。
一覧はこちら
- JSAF無料留学カウンセリング
-
まずはここから!無料留学カウンセリングにお越しください。
JSAFは、組織説明、プログラム説明や留学先選定、留学費用についてなど、個々に留学に関する相談を無料で受け付けています。
- JSAF留学セミナー・情報セッション
-
JSAFにて行われる留学セミナー・現地担当者による情報セッションのご案内です。
- 2024年05月15日2024年前期説明会 留学_何から始める_1年生
- 2024年06月12日2024年前期説明会 留学_何から始める_1年生
- 2024年06月07日2024年前期説明会 25年春から留学に行こう
世界トップ校への学部留学プログラム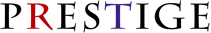 JSAF Prestige Study Abroad Program
JSAF Prestige Study Abroad Program
世界最難関大学への学部留学にチャレンジ!
詳細はこちら